第1回の記事では、私が現場で感じていた「指示待ちの子ども」への危機感と、
自分自身の関わり方に対するモヤモヤについてお話ししました。

今回は、その暗闇の中にいた私に一筋の光を投げかけ、教育観を根底から作り直してくれた
運命的な出会いについて綴ります。
それは、大学時代に触れ、現場に出てからその真価を思い知ることになった
『学び合い』(二重括弧の「学び合い」)という思想です。
この出会いがなければ、私は今も「教えること」に執着し、
子どもたちの可能性を無意識に摘み取る「親切な独裁者」のままだったかもしれません。
「教師が教壇に立ち、知識を授けるのが当たり前」
「子どもたちが静かに前を向き、先生の話を聞くのが良い授業だ」
そんな、私が疑うことすらなかった「教育の常識」が、音を立てて崩れ去った日があります。
私を救い、そして「添育(そういく)」という新しい看板を掲げることにつながる覚悟をくれたのは、上越教育大学の西川純教授(現在は退職)が提唱する『学び合い』という考え方でした。
初めてその理論に触れたとき、私の心に走ったのは「感動」ではなく、むしろ「拒絶」に近い衝撃でした。
なぜなら、そこには「教師の存在意義」を真っ向から問い直す、厳しくも温かい哲学があったからです。
「一人も見捨てない」という、美しくも過酷な覚悟
『学び合い』の根底に流れているのは、非常にシンプルで、かつ究極の願いです。
「学校は、多様な人々と折り合いをつけながら、自らの課題を解決する力を育む場である」
「一人も見捨てない教育を、社会を実現する」
この言葉に出会ったとき、私は自分の甘さを突きつけられた気がしました。
一斉指導の授業では、どうしても「平均的な児童生徒」に向けた解説になります。
そうすると、既に理解している成績上位群は退屈し、理解に時間が掛かる層は置いてけぼりになってしまう。
教師が前で喋れば喋るほど、皮肉にも「見捨てられる子」が生まれてしまう構造があるのです。
『学び合い』の授業では、教師は授業の冒頭、たった数分でこのように語ります。
「今日の目標は〇〇です。クラス全員が〇〇をできるようになってください。方法は皆さんに任せます。さあどうぞ。」
あとは教壇から移動し、一人の「観察者」に徹する。
「それは放任ではないのか?」
「先生が教えなかったら、子どもたちは遊んでしまうのでは?」
最初は私もそのように思いました。
しかし、現場で実際にこうした「授業」を試みたとき、
私の目の前に広がったのは、全く想像していなかった光景でした。
教壇から動いて見えた、学びの「本当の姿」
覚悟を決めて「教えること」を手放したあの日。
教室は一瞬、静まり返りました
子どもたちは戸惑い、互いに顔を見合わせたりします。
しかしそれもつかの間、一人の子が隣の子に声を掛け始めました。
「ねえ、ここ、どういう意味?」
「あ、それはね……」
そこから、教室が沸騰したように動き始めました。
普段は大人しくて発言しない子が、得意な友達を捕まえて必死に質問している。
勉強が得意な子が、ただ答えを教えるのではなく、
相手が分かるまで言葉を選んで丁寧に説明している。
さらには、クラスのあちこちで
「あっちのグループ、まだ終わってないみたいだよ」
「助けに行こうぜ」
という声が上がり始めました。
私がジョークを交えて解説しても、発問や板書を工夫しても引き出せなかった、
「当事者意識」と「熱量」が、そこには渦巻いていました。
私は教室の隅で、震えるような思いでその光景を見つめていました。
「ああ、子どもたちには、こんなにも自力で育つ力があったんだ。今まで彼らを『教えられないと動けない未熟な存在』だと決めつけていたのは、他ならぬ私自身だったんだ」
私の「丁寧な教育」という名の過干渉が、彼らの「天然の学ぶ力」に蓋をしていた。
その事実に気づいた瞬間、私のエゴは粉々に砕け散りました。
「信じて任せる」ことは、最大の技術である
『学び合い』を実践して分かったのは、教師が「教える」のをやめることは、
「決して楽をすることではない」ということです。
むしろ、教えるよりもずっとエネルギーを使います。
目の前で子どもたちが悩み、沈黙し、時には間違った方向に進みそうになるのを、グッとこらえて見守る。
「先生、教えて」という甘えの誘惑を断ち切り、「あなたたちならできるよ」と背中を押し続ける。
これは、深い「信頼」がなければ不可能な、高度な技術です。
大人が「熟達者」として上に立ち、答えを与え続けている限り、子どもたちは永遠に「未熟なフォロワー」のままです。
しかし、大人が横に立ち、彼らの可能性を信じて丸ごと任せたとき、
子どもたちは初めて「自分の人生の主役」として歩み始めます。
この「信じて、任せて、添う」という姿勢こそが、
私の提唱する「添育(そういく)」の心臓部になりました。
『学び合い』を社会に、家庭に広げたい
大学で出会ったこの『学び合い』という思想は、
私に「教育の本当のゴール」を教えてくれました。
それは、テストで良い点数を取らせるというレベルのことに留まらず、
「自分も周りも大切にしながら、自律して生きていける人間を育む」というレベルのことです。
しかしこの素晴らしい哲学は、まだ「授業手法」の一つとして語られることが多いのが現状です。
「信じて任せる」「一人も見捨てない」「育ちに寄り添う」というエッセンスは、
教室だけでなく、家庭での育児や、会社でのマネジメントなどなど、
あらゆる「人の育ち」の場面で必要とされているのではないでしょうか。
だからこそ、私はこの思想をさらに一般化し、誰もが日常で実践できるカタチにしたいと
考えました。
それが「添育(そういく)」という新しい挑戦です。
結びに:暗闇を抜けて
第1回で感じていた「指示待ちの子ども」という事実から抱く怖さ。
それは、『学び合い』という「信じる教育」に出会ったことで、「希望」へと変わりました。
「子どもには、自ら育つ力が備わっている」
この確信をさらに深めてくれたのが、教員としてのキャリアを一時停止して飛び込んだ、
現在の「育休」という時間でした。
学校という枠組みを離れ、24時間わが子と向き合う中で、
私はさらなる衝撃的な発見をすることになります。
次回は、「0歳児が教えてくれた、教えられなくても自ら育つという事実」
教科書もなく、先生もいない中で、
わが子がどのようにして「自律」のスイッチを入れていったのか。
家庭での添育の原点についてお話しします。

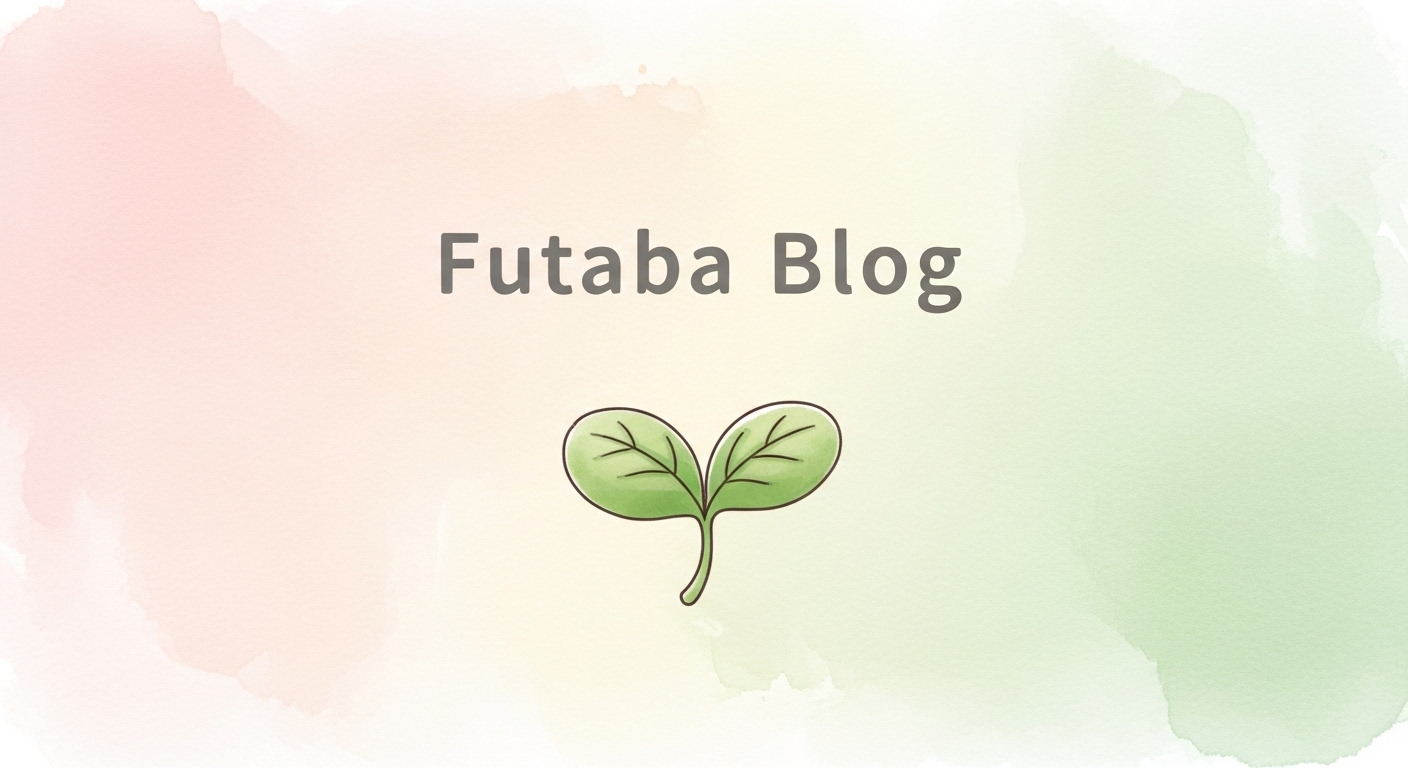



コメント