公立小学校の教壇に立ち、十数年。
私はこれまで、何十人、何百人もの子どもたちと向き合ってきました。
その中で、何度も耳にしてきた、ある「定番のセリフ」があります。
「先生、次はどのページをやればいいですか?」
「先生、ここは何色で塗ればいいですか?」
「先生、これ終わったんですけど、次は何をすればいいですか?」
キラキラした瞳で、真っ直ぐに私を見上げて聞いてくる子どもたち。
一見すると、やる気に満ちた、素直で可愛らしい質問です。
かつての私は、こうした問いに対して、
「はい、次は計算ドリルの15ページをやってね。それが終わったら読書だよ」というように、
効率的な指示を即座に出せることが「デキる教師」の証であり、務めだと思っていました。
教室は静かで、みんなが私の指示通りに動いている。
予定通りに授業が進む。
若い頃の私は、そんな「整然とした教室」を見て、ある種の満足感すら覚えていたのです。
しかし…
正直に白状します。
教員生活を重ね、さまざまな子どもたちと関わり、その後の成長を見ていくうちに、
「先生、次は?」
という言葉を聞くたび、私の中で小さな、しかし無視できない、
確かなモヤモヤが広がるようになってしまったのです。
それは次第に、日本の教育の未来に対する、ある種の「小さな怖さ」へと変わっていきました。
完璧な「指示待ちくん」を育てていないか?
「次は何をすればいい?」と頻繁に聞きに来る子は、
クラスの中でもいわゆる「良い子」とされることが多いです。
授業態度は真面目。
先生の意図を素早く汲み取り、言われたことを完璧にこなす。
トラブルも起こさないし、テストの点数も悪くない。
しかし、ふと立ち止まって、彼らの様子をじっくりと観察してみました。
例えば、「今日は自分の好きな課題を見つけて自由に取り組んでいいですよ」と投げかけた時。
彼らの多くは、途端にフリーズしてしまいます。
キョロキョロと周りを見渡し、不安そうに私の顔色を窺うのです。
もしかして彼らは「大人の許可」がないと、動けないようになってしまっているのではないか?
- 自分が今、本当は何を学びたいのか?
- 自分が今、何につまずき、何に困っているのか?
- 目の前にある空白の時間を、どう使えば自分のためになるのか?
人生を切り拓くために大切な、こうした「自分で自分を調整する力」を、
彼らはどこかに置き忘れてきてしまっている。
いや、違う。
彼らが忘れたんじゃない。
私が、奪ってきたんだ。
私が先回りして「丁寧すぎる指示」を出し続けることで、
彼らが本来持っていたはずの「自分で考える力」を奪ってしまっている。
私が「親切な先生」であればあるほど、子どもたちの自律の芽を摘んでしまっている。
その事実に気づいた時、私は背筋が凍るような思いがしました。
私は教育者として、とんでもない間違いを犯しているのではないか、と。
20年後の彼らを想像して震えた
この「小さな怖さ」は、彼らの将来を想像した時に、さらにリアルなものとなりました。
今、目の前にいる彼らは小学生です。
私が指示を出せば、素直に従ってくれます。
しかしあと10年、20年経ったらどうでしょう。
彼らは社会に出て、荒波の中で自分の人生を舵取りしていかなければなりません。
変化の激しい現代社会において、「正解」を知っている上司やリーダーが常にそばにいて、
手取り足取り教えてくれるでしょうか?
もちろん全くのゼロではないにしろ、なかなかそうした状況、環境は考えにくいでしょう。
もし彼らが、
「上司が指示してくれないから動けません」
「マニュアルに書いてないから分かりません」
という大人になってしまったら……。
そう考えた時、教室で響く「先生、次は?」という無邪気な声が、
まるで未来の彼らからのSOSのように聞こえてきたのです。
今のままの教育を続けていたら、彼らは社会の荒波に放り出された瞬間に、
遭難してしまうかもしれません。
目先のテストの点数の向上や、見かけ上の「良い子」を育てることに必死になるあまり、
彼らが一生を生き抜くための「最も大切なOS(基本ソフト)」をインストールすることの大切さを
私たち大人は忘れているのではないか。
そんな危機感が、私の中で爆発しました。
つい「親切」になってしまう、大人の事情
では、なぜ私たちは、ついつい先回りして指示を出してしまうのでしょうか。
これは学校の先生だけでなく、子育て中のパパさんママさんにも共通する悩みかもしれません。
正直なところ、
「その方が早いから」「失敗させたくないから」「揉め事を起こしてほしくないから」という、
大人の都合が大きいのではないかと思います。
学校現場は常に時間に追われていますし、親だって忙しい。
子どもが自分で考えて動くのを待つよりも、大人が答えを教えた方が、
その場はスムーズに回ります。
しかしそれだけではありません。
「正解を知っているのは自分だ」「未熟な子どもを導いてあげるのが大人の役割だ」という、
無意識の思い込み——あえて強い言葉を使えば「傲慢さ」が、私の中にあったのかもしれません。
大人が安全なレールを敷き、脱線しないように見張り、行き先を拡声器で指示する。
そのレールの上を歩いている限りは、大人も子どもも安心ですが、
いざそのレールが途切れたとき、子どもたちはどうすればいいか分からず、
立ち往生することとなってしまいます。
「私が良かれと思ってやっている(やっていた)『親切』は、
本当にこの子たちの未来のためになっているのだろうか?」
この消えないモヤモヤが、私に「教育」という営みのあり方を、
根底から問い直させるきっかけとなりました。
答えは既存の「教育」の外にあった
この違和感から逃げずに、うーんと悩み抜いた末、私は一つの結論に達しました。
これまでの「教育(Education)」の枠組みの中だけで考えていては、この問題は解決できない、と。
「教育」という言葉には、「熟達者が未熟者を導く」「上から下へ知識を授ける」という、
強い縦のイメージがどうしてもつきまといます。
もちろん、そうした導きが必要な場面もあります。
しかし、今の時代に求められているのは、それとは対になる、もう一つのアプローチです。
それが、私が提唱する「添育(そういく)」という考え方です。
文字通り、子どもたち(学習者)が「自ら育とうとする力」に、大人がそっと「添う」こと。
大人が主導権を握ってグイグイ引っ張るのではなく、
子どもが主役の「育ち」に、大人が伴走者として寄り添う。
勇気をもって主導権を子どもに返し、大人は環境を整え「信じて待つ」ことに徹する。
なんて偉そうに語っていますが、漠然とした思いをこうして言語化できたのは、生成AIのおかげ笑
そして、私の教育観をハンマーで砕いてくれた、ある運命的な出会いのおかげでもあります。
次回は、私が大学時代に出会い、私の人生と教育観を根底から覆した
『学び合い』という教育論についてお話しします。
教師が「教えること」を手放したとき、教室に一体どんな「奇跡」が起きたのか。
私の「添育者」としての物語は、あの時から既に始まっていたのです。

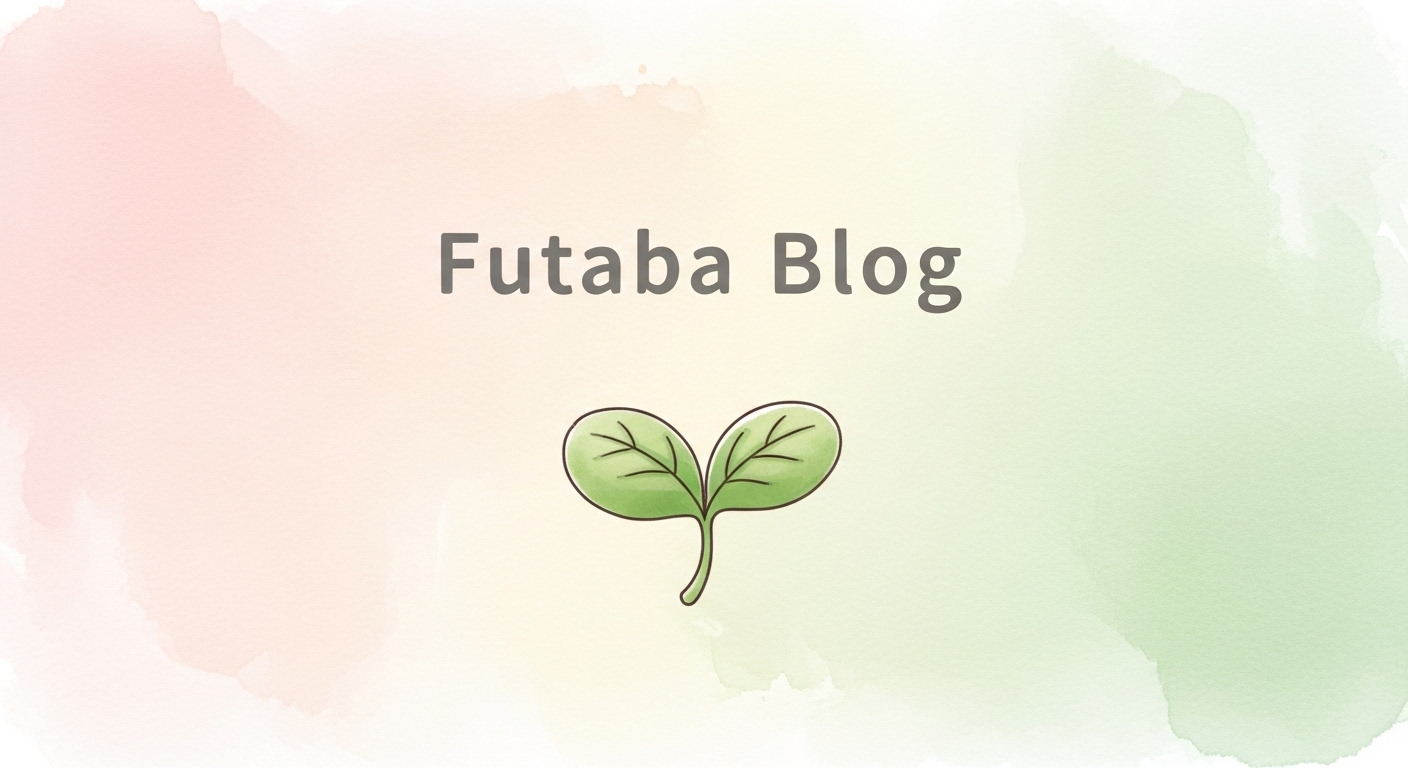



コメント